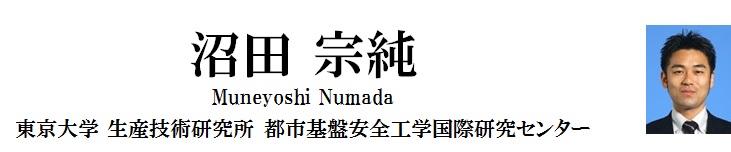沼田宗純の主な研究テーマをご紹介します.
私の研究の特徴はハードとソフトの両面からのアプローチである.
例えば,耐震補強を例示すると,耐震補強技術は世の中には多くあるが,
実際には補強を必要とする建物は多くあるが,補強を実施するまでにはいたっていない.
それは技術の問題ではなく,社会制度や仕組みの問題の解決が求められている.
したがって,ハードとソフトの両面の研究をしなければ課題を解決したとはいえない.
主な研究テーマ
ハード的な研究
・EDEM(拡張個別要素法)による河床地盤の運動を考慮した土石流シミュレーション
・LPFDM(ラグランジアン粒子有限差分法)による土砂崩壊過程の数値モデル
・地すべり土砂の変形を支配するパラメータの研究
・地震による石垣の動的挙動解析
・組積造構造物の補強技術
ソフト的な研究
・効果的な災害医療情報の収集と活用
・現象先取り減災行動誘導型災害報道の構築
・言語体のランニングスペクトル解析手法の開発
・災害対応業務分析
・効果的な防災計画の立案
・防災巻きによる防災教育者の養成
その他の活動
・被害調査(インドネシア:パダン,トルコ:ワン,新潟県中越地震,東日本大震災など)
・防災教育
・研究会(防災ビジネスの創造と育成の研究)
研究の概要
学士,修士,博士論文のテーマまで一貫して地盤の大変形解析の研究を行っている.
学士論文のテーマは,個別要素法による土石流のシミュレーションであり,粒形の違いに着目し,土石流がどのように挙動するのかを動的に解析した.
修士論文のテーマは,LPFDM(Lagrangian Particle Finite Difference Method)による地盤の大変形解析手法を開発した.
これはオイラー座標系とラグランジアン座標系を組み合わせ,その座標空間内を粒子が移動することで,
大変形解析においても計算が破綻することなく,シミュレーションできる技術である.
博士論文は,地すべり土塊の形状と到達距離の関係を考察し,新たな理論的枠組みを構築している.
これは数値解析の結果と実際の地すべりの現場との比較によりシミュレーションの精度検証を行っている.
2004年の新潟県中越地震による地すべりの現場において,その挙動をバックリング現象との関係で考察したものである.
これまで大学院教育においては,ハード(実験,数値解析,観測など)とソフトの両者について教育・研究を行っている.
また,首都直下地震防災・減災特別プロジェクト(文部科学省)など,外部の研究プロジェクトにも積極的に参画してきた.
また産学連携においては,企業との共同研究も積極的に行い,防災ビジネス研究会(RC63,RC77)では,研究会の運営,報告書の取りまとめを5年間継続し,
30社以上の企業と防災ビジネスの研究を行っている.
構造物の脆弱性評価と対策とこれを実現する制度設計
国際的な視点で地震被害の軽減を図るためには,組積造構造物の崩壊による被害を減らさなければならない. 私はこれまで組積造構造物の補強を推進するために,技術開発と制度設計の研究を行ってきた. 技術開発に関しては,既に提案されていたPPバンドメッシュ工法の普及に努めてきた. 制度設計に関しては,保険制度やインセンティブを用いた研究を実施してきた. その一方で,次のような工夫も行ってきた.Bambooバンドによる補強方法の提案,組積造建物の強度を向上させるためのFRPを用いた工法の提案,高強度繊維塗料による補強方法の提案などを行い,動的破壊挙動を実験と数値解析を用いて研究してきた.この経験を通じ,そもそも制度設計を行う上で,建物や地域の脆弱性を評価するモデルが存在していないことが根本的な課題であり,この評価モデルの構築が急務であると考えた.私は防災プロセス工学の枠組みの中で,この評価モデルを確立し,事前対策と事後対応の適切な重み付けにより,事後対応の限界と事前対策の有効性を示すことで,組積造構造物の補強が推進する制度設計を成立させていく.
地域防災計画と災害対応業務
土木学会の地域防災計画特定テーマ委員会のメンバーとして,地域防災計画のあるべき姿を検討し,地域防災計画の策定と運用に関するガイドライン」の作成に参画した.また,首都直下地震防災・減災特別プロジェクト(文科省)にも参画し,広域的危機管理・減災体制の構築に関する研究において,神奈川県,横浜市,川崎市の3者の地域防災計画を比較する中で,自治体間や行政部局間での災害対応業務の違いを分析した.これらを踏まえ,福島県矢吹町の地域防災計画の見直しを行い,従来とは異なる革新的な地域防災計画を提案,実証している.地域防災計画の作成において,専門家の不在の問題,予算の制約の問題等を解決することができ,研究段階から実践段階への適用までの手続きを構築したことは本活動のユニークな点である.
災害情報のマネジメント
災害情報は,災害報道と災害医療の2点に力を入れてきた. 災害報道については,「現象先取り・減災行動誘導型報道」の構築を目指し研究している. その中の一つとして,東日本大震災の報道について,報道の過集中を被害との関係やこれがもたらす義援金などへの影響等を定量的に示したことは本研究の大きな成果である. また,災害情報を時空間的に分析するために,ランニングスペクトル解析法を開発したことをも特徴の一つである.これらの成果は,東日本大震災後,マスメディアでも取り上げられ,社会へ災害報道のあり方を提案したものとしてその影響は大きい.また,これらの成果は,独立行政法人 大学評価・学位授与機構から「東日本大震災における大学対応の評価分析」を依頼されるなど発展している.災害医療については,患者情報のリアルタイム動的把握システム(TRACY)を開発した.これは,都市部で多くの方が保有しているFeliCa機能を用いたものであり,平時と災害時の両者の利便性を取り入れた視点はとてもユニークである.これは,山梨大学医学部付属病院,静岡県立総合病院という大病院の中で実証実験し,その有効性を確認している.この実証実験では,病院職員,地域住民,行政職員,マスコミ関係者などからも協力を得たものである.
防災教育
防災教育として,教育委員会や小中学校において,学校の先生方や生徒に対し,18回の防災研修会やワークショップを行い,約780名に講義を行ってきた.これらの実績から渋谷区教育委員会から学校運営協議会の委員を委嘱されている.私の防災教育の大きな特徴は,「防災教育を実施できる先生」を育ててきた点である.そのうちの先生の一人は「花まる先生」として大きく取り上げられるなど,防災教育現場に対して大きな貢献をしてきた.これらの成果が認められ,文部科学省の平成26年度健康教育行政担当者連絡協議会において,全国の教育委員会などの研修会でも講師を行っている.今後は,教育委員会を中心として,多くの防災教育が実践できる先生を教育していく予定である.
国際的な活動
学会の活動としては,2009年インドネシアスマトラ沖地震に関して,土木学会の復旧協力チームとして,橋梁,ライフライン施設の被害調査を担当した. また,2011年トルコ・ワン地震では,日本地震工学会の被害調査の学会代表として被害調査を行い建築学会との連携を図った. さらに,世界地震工学会議WCEE(15th World Conference in Earthquake Engineering)では若手ワークショップ(Lisbon in Motion workshop)において,唯一の日本人として参加し,その後の国際交流にも発展している. 研究活動としては,私の研究テーマを全て国際社会においても適用可能な仕組みとして,構築することを考えている.組積造構造物の脆弱性評価については,中国では,中国発展基金会の支援の下,チベット自治区ラサ市への展開のための現地調査ならびに工程力学研究所(ハルビン市)において,振動台による共同実験を行い,私は現場で指導的な立場を担った.また,インドネシアでは,バンダアチェ市の孤児院建物を対象に,耐震補強の実適用を行い,現地のエンジニアへの教育と施工指導を行った. 地域防災計画については,一連の研究成果を米国ロサンゼルス市の危機管理局に提案に行くなど,積極的に国際的な活動を行っている.アメリカではICSという危機管理システムがあるが,私の研究ではより細かな災害対応業務を規定しており,これがアメリカでも活用の可能性があるとの意見交換を行った. 災害情報については,フランスのパリにあるESIEE Parisに研究成果を提案,フランスへの展開を目指す等の活動を行っている.これは1998年から2001年に生産技術研究所でVisiting scientistとして活躍されたTarik Bourouina教授との関係で実現したものであり,海外展開,異分野との融合,生産技術研究所のネットワークや環境を十分に活用させて頂いたものである.